「夫が1000万円の預金を残して亡くなりました。
夫は、5年前、長男に4000万円の自宅購入資金をあげました。
また夫は、3年前、二男に3000万円の自宅購入資金をあげました。
妻の私は、いくら遺産をもらえるのですか?」
このようなご相談をお受けすることがあります(実際のご相談は、事案がより複雑です)。
遺産分割では、夫の死亡時に残っている遺産の額に、長男と二男が夫から受け取った贈与の額を加えて、それぞれの取り分を計算していきます。
妻の法定相続分は2分の1、長男と二男の法定相続分は各4分の1ですので(民法第900条)、妻が夫の遺産から取れる金額は以下の通りとなります。
遺産分割のベースとなる金額:1000万円+4000万円(長男への生前贈与)+3000万円(二男への生前贈与)=8000万円
妻の本来の取り分:8000万円×1/2(妻の法定相続分)=4000万円(①)
妻の現実の取り分:1000万円(②)←現存する夫の遺産が1000万円の預金しかないため、妻は本来の取り分である4000万円の一部しか取れない。
それでは、妻は、1000万円を超える金額を取れないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
民法では、相続人が最低限もらえる遺産の取り分についての定めがあります。
この取り分のことを「遺留分」といいます。
妻の遺留分は、妻の法定相続分2分の1の半分である4分の1です(民法第1042条)。
妻の法定相続分による取り分は4000万円(①)であるため、妻の遺留分は、その半分である2000万円(③)になります。
妻の遺留分:4000万円(①)×1/2=2000万円(③)
妻は、夫の遺産から現実に1000万円(②)を取れているので、妻の遺留分の不足額は1000万円(④)になります。
妻の遺留分の不足額:2000万円(③)–1000万円(②)=1000万円(④)
それでは、妻は、遺留分の不足額1000万円(④)を、どのように回収するのでしょうか?
民法では、新たに贈与を受けた者から順に、遺留分の不足額を請求されることになっています(民法第1047条第1項)。
質問の事例では、長男が夫からお金をもらった日付は5年前、二男が夫からお金をもらった日付は3年前ですので、妻は、新たに贈与を受けた二男に対し、遺留分の不足額1000万円(④)を請求することになります。
このように、妻は、夫が残した預金1000万円(②)を受け取り、かつ、二男から遺留分の不足額1000万円(④)を受け取り、計2000万円(③)の遺留分を確保することができるのです。
遺留分については、ベースとなる金額の計算、遺留分の計算、遺留分の不足額(侵害額)の計算、誰にいくら請求できるかの計算が、大変複雑です。
そのため、生前贈与が絡む遺産分割については、計算ミスを防ぐために、必ず弁護士の相談を受けておくべきでしょう。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和
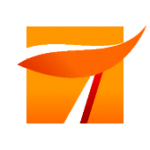 垂水駅前法律事務所
垂水駅前法律事務所